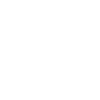東京プロジェクト
スタディとは?
Tokyo Art Research Lab「思考と技術と対話の学校」で展開する、
アートプロジェクトの核をつくるための実践です。
“東京で何かを「つくる」としたら”という投げかけのもと、
「ナビゲーター」と、公募で集まった「メンバー」がチームとなり、
スタディ(勉強、調査、研究、試作)を重ねます。
2020年度は、アーティストやディレクター、デザイナーなど、
関心や属性の異なる3組の「つくり手」がナビゲーターを担当。
演劇、美術、パフォーマンス、写真、映像など、
表現方法や「つくる」過程もさまざまです。
それぞれのスタディには、アーツカウンシル東京のプログラムオフィサーが伴走し、
学びのサポートをしていきます。
このウェブサイトは、3つのスタディがどのように
「何かをつくる手前の時間」を過ごしたのかを記録するものです。
何を、誰と、どのように向き合ったのか。
スタディの活動と、同時期に並走するナビゲーターたちの創作活動に目を向けます。
そのプロセスや、そこで生まれたことばや手法を蓄積する素材庫は、
いつかの誰かの「つくる」ヒントになるかもしれません。
わからなさ、複雑さ、そしてときに遠回りすることを大事にしながら
予定調和に陥らない「つくる時間」に身を置く実験を、
ぜひ追体験してみてください。

Tokyo Art Research Lab (TARL)
アートプロジェクトを実践する人々にひらかれ、共につくりあげる学びのプログラムです。
人材の育成、現場の課題に応じたスキルの開発、資料の提供やアーカイブなどを通じ、
社会におけるアートプロジェクトの可能性を広げることを目指しています。
https://tarl.jp
「東京プロジェクトスタディ」ウェブチーム
ウェブディレクション:萩原俊矢
ウェブサイトデザイン:井山桂一(GRANDBASE inc.)
プログラミング:萩原俊矢、多田ひと美(GRANDBASE inc.)
編集方針設計:川村庸子、高橋創一
全体設計:坂本有理(アーツカウンシル東京)
企画:上地里佳、岡野恵未子(アーツカウンシル東京)
イメージビジュアル:加藤亮介